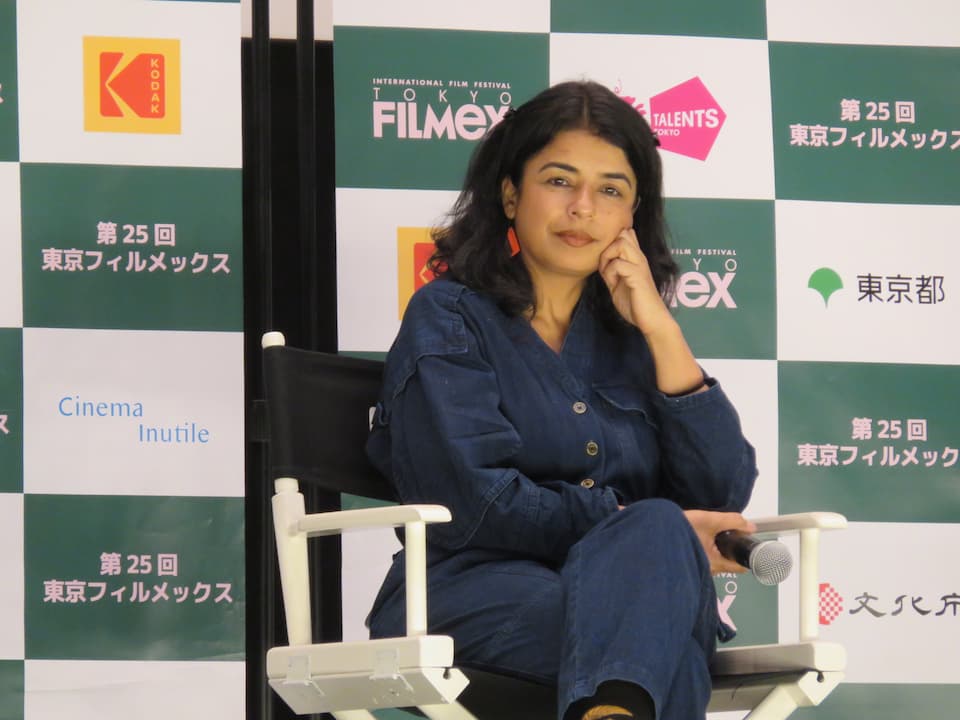インド社会の暗部に斬り込む
「サントーシュ」は、殉職した夫の後を継いで警察官となったヒロインが殺人事件を捜査する姿を通して、インド社会の闇を暴いた作品だ。
夫が殉職すると未亡人は亡夫の職を継承できる――インドにそんな制度があることを、この映画で初めて知った。一家の大黒柱を失った遺族が路頭に迷わずに済むように考案された救済システムなのだろう。金銭で保障するより働いて稼いでもらったほうが、政府としても助かるということだろうか。
サントーシュは迷うことなくこの制度を利用する。しかし、飛び込んだ警察組織は、絵に描いたようなマッチョ社会。あからさまな女性差別がまかり通り、階級差別も露骨である。戸惑うサントーシュだったが、順応せざるを得ない。
そこにベテランの女性警官、シャルマ警部が赴任してくる。その指揮下に入ったサントーシュは、優秀で自信に満ちたシャルマに心酔し、めざすべき目標と思い定める。

そんなサントーシュが担当することになったのは、ある少女の暴行殺人事件。殺害された少女の遺体が井戸で発見されたのだ。
ところが、ろくに捜査もしないうちに、犯人は早々と特定されてしまう。別に真犯人がいるのではないか。疑問をいだいたサントーシュは “触れてはならぬ”領域へと踏み込んでいく。
被害者の少女はいわゆる不可触民。別の意味で“触れてはならぬ”存在である。カーストの最下層に位置する少女など、上位カーストにとっては人間ではない。人間ではない者をレイプしようが、殺害しようが、大した問題ではないのだ。
このおそるべき差別感、そして、その基盤をなす階級社会のおぞましさ。上位カーストは警察組織にガードされ、悪事のし放題なのだ。経済発展めざましい大国インドだが、いまなお残るカースト社会の闇は絶望的なまでに深い。
本作は、女性警官を主人公に据え、その屈辱的な仕打ちを描くことで、インド社会に蔓延(はびこ)る性差別に対しても痛烈な批判を加えている。サントーシュの尊敬するシャルマが、しだいに自立を失い、男性社会に同化していく姿は実に痛ましい。
カンヌ映画祭のある視点部門で上映。第97回アカデミー賞国際長編映画賞部門のイギリス代表作品にも選ばれている。